| cover | ||
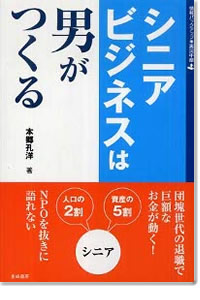 |
シニアビジネスは男がつくる | |
| contents | お買い求めはコチラ |
本郷孔洋公認会計士・税理士/辻・本郷税理士法人 理事長
シニアビジネスの異業種交流会(ゴールド倶楽部)をはじめてあっという間に二年が経ってしまいました。この交流会をやるとき、私は心に決めたことがあります。それは、単なる勉強会にしない。ぜひ、この会から、新しいシニアビジネスを生みだしたい。そして、私自身もシニアビジネスに「深くかかわりたい」ということでした。 職業柄、今まで随分と勉強会を開いたり、参加してきました。でも単なる勉強会では、すぐに飽きてしまい、あまり長くは続かなかったのです。ですから、この会だけは従来とは違い、勉強会の場を通じて実践したり、起業する場にしたいと考えていたのです。 シニアビジネスは、本当に多種多様です。 職業柄、私はたくさんの企業を人より多く見てきたはずですが、それでも、シニアビジネスは広く、バリエーションがあり、とても奥が深い。また、実際にはじめてみてわかったのですが、シニアビジネスは知恵が勝負です。小資本でできますし、在庫のリスクもないし、粗利の高い商売もできる。まさに、大会社の社内ベンチャーとしてもできるので、起業も可能である。私自身、あっという間に、シニアビジネスにはまってしまいました。 「知行合一」という言葉があります。陽明学の言葉ですが、私は勝手に次のように解釈しております。「認識し、知識を得ることと、行動、実践することは同じことだ」と。 豊かな社会になりますと、どうしても知識が先行し、リスクを恐れるあまり無謀な行動ができなくなります。行動する人が勝てる社会になりました。 それもあり本書は、読むだけではなく、行動して欲しいという願いを込めて書きました。 あなた自身が、十分シニアビジネスのリーダーになりうるチャンスがあるからです。 シニアビジネスは男がつくる 「愛は平和ではない。愛は戦いである。武器のかわりが誠実であるだけで、それは地上における、最もはげしい、みずからを捨てていかなければならない戦いである」(梶原一騎原作、ながやす巧劇画 講談社) 図太い恋愛マンガと言われた『愛と誠』のはじまりです。 これから団塊シニアが大量に出ます。どのメディアを見ても、盛んにシニアビジネスの話題があがります。しかも、女性が市場をリードするという話が大半です。でも、私の意見はまったく逆です。 たとえば団塊世代は、日本の高度成長の波に乗った、企業戦士たちの集団です。 「愛だって戦い」を経験した男が、大量にシニアマーケットに参入してきます。給料日には、「ニクを食べたい!」と即答し、「しゃぶしゃぶ食べ放題ニッキュッパ」などと言って肉も死ぬほど食べて具合が悪くなった世代です。『巨人の星』『あしたのジョー』に熱中したスポコン世代です。 一言でいいますと、男性の一時代を作った人たちです。この人たちがシニアマーケットに参入してきたら、男の時代が再来すると思いませんか? スポコンで鍛えた、大量の企業戦士がシニアに参入します。スポコンシニアの時代がくるのではないかと冗談ではなく、本当に思っています。 今は女性の時代で、「女性がわからなければビジネスではない」と言われています。でも、考えても見てください。いつもテレビの前で謝ってばかりいる会社役員、オレについて来いと言えなくなった男達。こんな男ばかりを見ていたら、女性は強い男を求めると思いませんか? 逆張りで言いますと、シニアビジネスは男のマーケットです。男に焦点を当てたほうが、少なくとも収益が高いビジネスが取れるのではないか? まずこれが、本書で伝えたい第一のポイントです。 男はピラニアになれるか? 老人ホームの比率は八対二で女性が多い。男はもてるそうです。もっとも現役のときに偉かった人は威張るのでダメだそうですが。 シニア向けパソコン教室も、グループ分けすると女性五人につき、男性一人を入れないとグループが持たないそうです。男がキーパーソンになっているではありませんか。 聞いた話ですが、「サンマの輸送にピラニアを一匹入れると、何匹かはサンマが食われるそうですが、皆元気のままでいられる」そうです。 その手の話は江戸時代のニシンの輸送に、なまずを入れて輸送するのと酷似しています。ニシンだけだとぬるま湯で、ダメになるたとえです。 これを見てもシニアビジネスは、男が主役になるのではないか、ピラニアか、なまずの役割をするのではないかと思うのです。希望と願望を込めてあえてそう言いたい。 粗利の高い商売をやれ 本書はシニアビジネスに興味がある会社、漠然とシニア社会を考えている企業人、そして今でも近い将来、ベンチャーとして起業したいと思っている人のために書きました。アメリカのベンチャーキャピタルは、粗利の低い商売にお金を出さないと言われています。私も職業会計人として、数々の起業や新規事業の相談に長年たずさわって来ました。 まず、「即座にやめなさい」と言いたいのが、粗利の悪い商売です。そして在庫のリスクが高い商売、競争が激しい、値段がとれない商売もです。 逆に言えば、小資本でできて、粗利の高い商売、競争の少ない商売なら、失敗してもリスクは少ない。 「ブルーオーシャン」という言葉が流行りました。(『ブルーオーシャン戦略』W・チャン・キム+レネ・モボルニュ著、ランダムハウス講談社刊) 時代は新しい競争のない市場、世界を創造する時代に移っています。 シニアビジネスは新市場ですが、粗利の高い商売が多いように感じます。これからは在庫のリスクが少ない競争がない、未開拓の市場が待っているのです。 実務家でもある私にとっては、将来も重要です。だが、今そこにあるお金を我が手につかむのが、ビジネスとしてもとても重要。すぐそこにお金があるのも、シニアマーケットです。膨大にお金を持っている市場であるからです。この市場を逃す手はありません。 満足できれば、価格は二の次 私のところにもしばしば、ビジネスの海外視察ツアーの案内が来ます。いつも気になるのですが、そのツアーはほとんどが、エコノミークラスに乗って、部屋も二人でシェアするというタイプの案内がほとんどです。「ああ、三〇年前とまったく同じだな」と思ってしまいます。 ところが、消費者だけはどんどん贅沢になっていきます。豪華クルーズがすぐ満杯になります。大阪のリッツカールトンでは、一泊七〇万円の宿泊が人気でした。 室内でのクラシックのミニコンサート付き、寿司職人の親方がその部屋で握ってくれるという、スイートルームの宿泊です。 ほんとかなと思い、リッツカールトンに宿泊したときに聞いたのですが、結構、利用する人がいるそうです(もっとも、私の友人は、「お客さん、アップグレードでどうですか?」と尋ねられ、一〇万円でそのコースを使ったと言っていましたが、真偽のほどはわかりません。私も一〇万円でできないかと言ってみたのですが、それは無理と即座に断わられました)。 ところが、今はなんとリッツカールトン、ドリームというプランを一日二〇〇万円で、自宅を訪問してサービスするという出張プランまであります(二〇〇六年九月一日(金)~二〇〇七年三月三十一日(土)料金〓一件 二、〇〇〇、〇〇〇円)。 このように消費者は、変化しているのです。 「香港のペニュンシュラホテルのスイートルームのバスルームと同じ設計をしてくれ」と依頼された設計士のうち、何人がそれに応えられるでしょうか。ビジネスホテルに泊まって、死ぬほど仕事をしているような設計士は、期待に答えられるのだろうか。 社会が成熟化してきますと、どんどん消費者は贅沢になります。経済も消費型になります。ところが、私の知っている限り、経営者がまだ三〇、四〇年前のもの作り発想のままで、頭の中は「贅沢は敵だ」という意識です。 でも、「贅沢は素敵だ」と「素」を入れただけで、発想が変ってきます。変わる消費者に比べて、変わらぬ経営者では、これからのシニア社会のビジネスに乗り遅れてしまいます。シニアビジネスは、値段に関係ないマーケットです。 これがシニアビジネスを行うに当たって、本書で強く言いたい私の最大のポイントです。 「シニアビジネスを勉強する前に、経営者は意識を変える」ことができなくては、本書を読んでもこれまた、無駄です。 なぜか誰もふれない膨大なマーケット シニアビジネスは、従来の介護のマーケットに加えて、元気な「アクティブシニアのマーケット」があると言われてきました。 ところが、シニアビジネスを勉強してみて未病にあたり、介護もいらない、でもピンピンもしていない。しかもアクティブでもない膨大なシニアがある、という確信にいたりました。 いわゆる病気でもない、かといって、ピンピンもしていない人たちです。私はこのマーケットを「未病マーケット」と呼んでいますが、この層が健康市場で一番サイズが実は大きいのです。 このゾーンのマーケティングが実は苦労するけど、究極のシニアビジネスではないでしょうか。このことも本書を書く大きなインセンティブになったのです。 私はこのマーケットを対象にしてすでに仕事をしている人に会ったとき、この未病マーケットを制覇した人は、シニアを制するといっても過言ではないな。そんな実感をもちました。 NPOを抜きに語れない 故ピータードラッカーが、ポスト資本主義は、非営利組織の活動が盛んになると言いましたが、たしかにボランティアを抜きにして社会活動は行えなくなっています(『ポスト資本主義社会』P・F・ドラッカー著 ダイヤモンド社刊)。 つくづくピータードラッカーは未来を予測する天才であると思いますが、二一世紀はボランティア経済でもあります。民営化だとか規制緩和と言いますとゴロがいいのですが、要するに「国はお金を出せない、勝手にやってください」ということです。 アメリカだけがなぜ、NPOが盛んになったかと言いますと、政府が面倒を見ないため、必然的にボランティアがやるしかなかったのです。医療保険が未整備だったアメリカでは、最初は国が何もしてくれないという問題を解決するために出発したのですが、なんと会員三〇〇〇万人にも組織化したAARPのような巨大なシニアのNPOが活動しています。 私は日本でも、今後同じ傾向になるなと、これもシニアビジネスに触れれば触れるほど、強く感じます。NPOとのコラボレーションがなければ、シニアビジネスは大きな成功がないだろうなと思うようになりました。 幸いなことに身近にNPOと一般企業の連携も見ましたし、商店街の活性化もNPO抜きではできないでしょう。本書ではこれについても、多くの紙面を割きました。 地方はシニアビジネスのネタがゴロゴロ シニアビジネスは地方から始まります。高齢化は地方が先に進んでいます。ですから、シニアビジネスに対する、優位性ははるかに都会より地方です。高齢化と過疎は、地方経済をネガティブに暗く表現しがちです。でも、シニアビジネスに関しては、とてもビックチャンスが地方で待っています。 また、シニアビジネスは、地方の方が立ち上げやすいのも事実。マーケットが狭いだけ、シェアが取りやすいし、競争も少ない。ましてやシニアビジネスは、これからのビジネスです。どこも圧倒的に強い会社はありません。早く、高いシェアが取れて、市場を支配できます。 行動力があり、スピードがあれば、圧倒的に支配できます。これも言いたかったことのひとつです。


 仕事の失敗DB
仕事の失敗DB
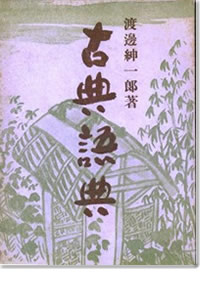 古典語典
古典語典 「公認会計士・税理士」は資格をとってからが勝負!
「公認会計士・税理士」は資格をとってからが勝負!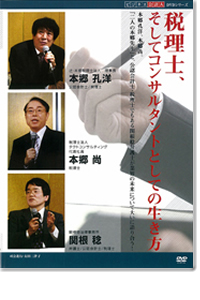 税理士、そしてコンサルタントとしての生き方
税理士、そしてコンサルタントとしての生き方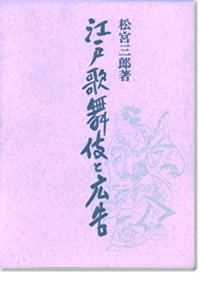 江戸歌舞伎と広告
江戸歌舞伎と広告 久里浜『アルコール病棟』より臨床三〇年の知恵
久里浜『アルコール病棟』より臨床三〇年の知恵 大ノーベル傳
大ノーベル傳 税務調査に強い税理士ご紹介
税務調査に強い税理士ご紹介 TOHO医療に強い税理士紹介センター
TOHO医療に強い税理士紹介センター 東峰書房ショッピングサイト
東峰書房ショッピングサイト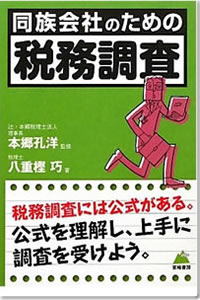 同族会社のための税務調査
同族会社のための税務調査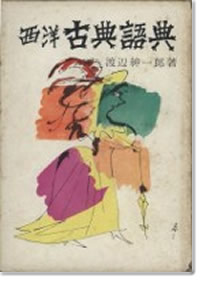 西洋古典語典
西洋古典語典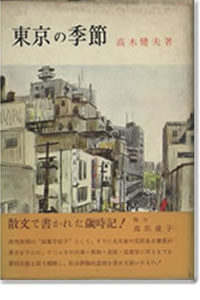 東京の季節
東京の季節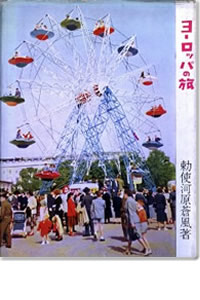 ヨーロッパの旅
ヨーロッパの旅 アルコール依存症はクリニックで回復する高田馬場クリニックの実践
アルコール依存症はクリニックで回復する高田馬場クリニックの実践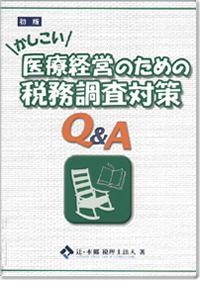 かしこい医療経営のための税務調査対策Q&A
かしこい医療経営のための税務調査対策Q&A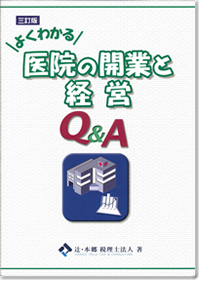 よくわかる医院の開業と経営Q&A
よくわかる医院の開業と経営Q&A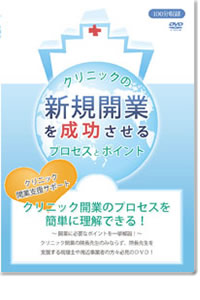 クリニックの新規開業を成功させるプロセスとポイント
クリニックの新規開業を成功させるプロセスとポイント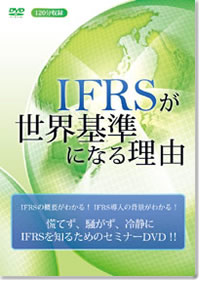 IFRSが世界基準になる理由
IFRSが世界基準になる理由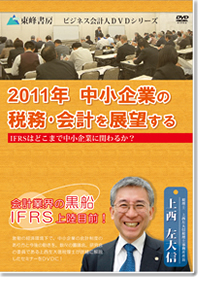 2011年中小企業の税務・会計を展望する~IFRSはどこまで中小企業に関わるか~
2011年中小企業の税務・会計を展望する~IFRSはどこまで中小企業に関わるか~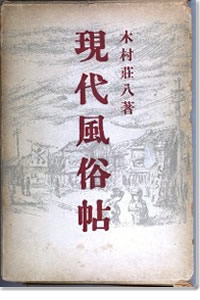 現代風俗帳
現代風俗帳 私のアルコール依存症の記ある医師の告白
私のアルコール依存症の記ある医師の告白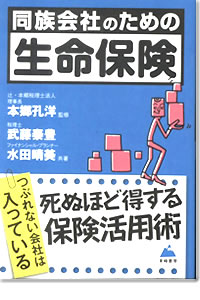 同族会社のための生命保険
同族会社のための生命保険 「税金経営」の時代
「税金経営」の時代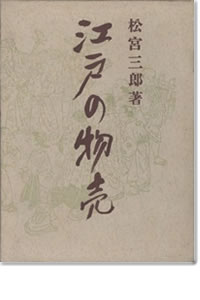 江戸の物売
江戸の物売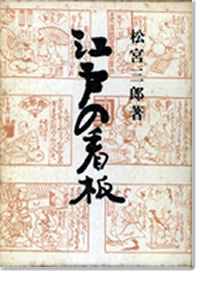 江戸の看板
江戸の看板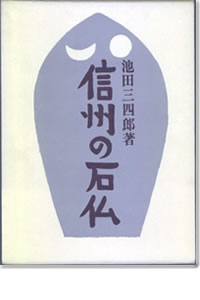 信州の石仏
信州の石仏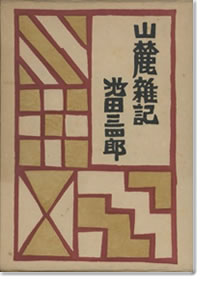 山麓雑記
山麓雑記 TOHO税務会計メルマガのご案内
TOHO税務会計メルマガのご案内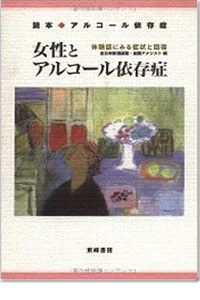 女性とアルコール依存症体験談にみる症状と回復
女性とアルコール依存症体験談にみる症状と回復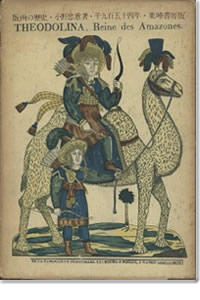 版画の歴史
版画の歴史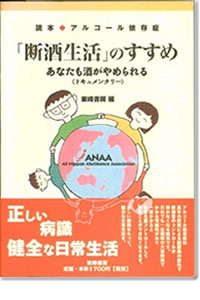 「断酒生活」のすすめあなたも酒がやめられる《ドキュメンタリー》
「断酒生活」のすすめあなたも酒がやめられる《ドキュメンタリー》 金融マン必携!相続税実践アドバイス
金融マン必携!相続税実践アドバイス 描きかけの油絵
描きかけの油絵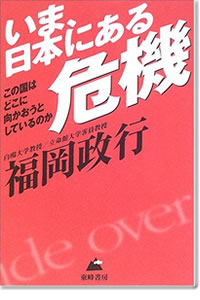 いま、日本にある危機
いま、日本にある危機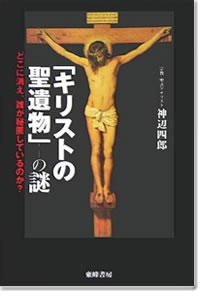 「キリストの聖遺物」の謎―どこに消え、誰が秘匿しているのか?
「キリストの聖遺物」の謎―どこに消え、誰が秘匿しているのか?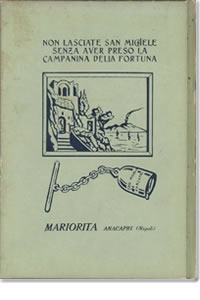 長生きの国を行く
長生きの国を行く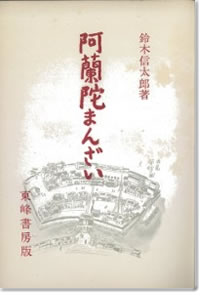 阿蘭陀まんざい
阿蘭陀まんざい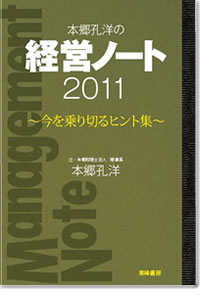 経営ノート
経営ノート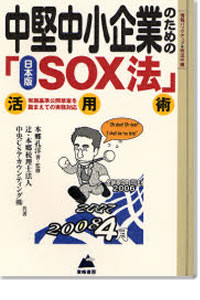 中堅中小企業のための「日本版SOX法」活用術
中堅中小企業のための「日本版SOX法」活用術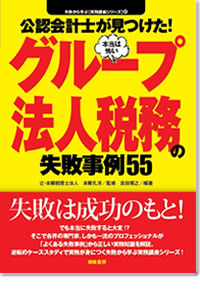 グループ法人税務の失敗事例55
グループ法人税務の失敗事例55